
【沖縄/古宇利島 | 持ち込みSUPスポット情報】水色の海×熱帯植物が覆い茂る雄大な南国リゾート

– Contents – ➖
今回のクルージングコース・SUP禁止場所を含む全体MAP
青・クルージングコース/黄・利用施設/緑・エントリーポイントまでのルート/赤・SUP航行注意ポイント
※各アイコンをクリックするとポイントごとの情報が見られます。
古宇利島SUPの見どころ
水色の海・サンゴ・白い砂・沖縄ならではの奇石・南国の植物で最高の気分!
目が覚めるように鮮やかな水色の海。
遠浅で白い砂と珊瑚礁の切れ目で色が変わるのがとても綺麗。

古宇利島は珊瑚礁の働きで形成された琉球石灰石でできています。
古宇利島の全周は約8kmあり、独特の形状の岩礁と南国独特の植物の景観が続きます。
海は穏やかで、なんとものんびりとした雄大さを感じられます。
普段のストレスなんて吹っ飛ぶ、期待通りとても気持ちの良いSUPクルージングが楽しめます。
SUPからだと鳥しか上陸していない浜にも上陸できます。

ハートロックなど景勝地もあり一周したかったのですが、風が予想よりも強くなってしまったため1/3程度進んだ後、途中で引き返しました(それでも大満足でした)。
駐車場
古宇利ふれあい広場の駐車場を利用しました。
奥側だと敷地も広めでSUPの準備もしやすかったです。

無料
トイレ・シャワー
トイレ
駐車場に併設
シャワー
上記トイレに腰の高さの水洗い場の併設がありますので、SUPボードを洗ったり手足を軽く流すの便利です。
(※但しSUP洗い時にボード全体に水をかけ流すのは何もないとやりづらいので、バケツやタンクのようなものは持って行った方が良いです。いつもはプラスチックのものを車に積んでいますが、旅行で遠征のため、折り畳みができるものをダイソーで購入し二つ持っていきました。)

▼ 準備・後片付けについて、参考にしていただける記事を作りましたので、合わせて見てみてください。
エントリーポイント
古宇利ビーチからエントリー
沖縄・古宇利島の気象について
風
私が入った日は北風4〜5m/s予報でした。(古宇利島の南から出航して北に向かって漕ぎ、帰ってくる時は風に押されて帰って来れる想定。古宇利島の南側は本島や屋我地島があるので流れ止めもあり安心感もある)
ただし体感的には予報よりもう少し強かったように感じました。
3月初旬の沖縄は、北風から南風に転換する時期で風が強めの日が多いようですので、無理しないこと・風向と立地の確認を怠らないようくれぐれも注意してください。
私の行った3日間は、沖縄本島は午後より午前の方が比較的風が穏やかな印象でした。
時期にもよるかもしれませんが、午後に向かって風が強くなる日ばかりでしたので、午前~暖かい14時頃を目掛けて活動をする方が穏やかで過ごしやすい気候でSUPを楽しめそうです。
波
時々リーフの切れ目か、波が高めの場所もありますが、全体的には穏やかでSUPしやすいです。
温度・服装
最高気温21℃予報でしたが本土と比べて全体的に日差しがかなり強く暖かく感じます。
お昼前後の11時頃〜14時頃は照り付けがかなり強く、汗ばむほどではないものの夏のように肌が焦げる感覚があり、ラッシュガードだけでも全然寒さを感じませんでした。
とはいえ水温は気温に比べて1ヶ月遅れでの上昇となるため体感としては冷た目で、3月初旬は北風の日が多いようで私が行った時も北風でしたので、ピーク時間を過ぎるとそれなりに冷えました。
私は長袖長ズボンのラッシュガードの上に3mmのセミドライのフルウェットスーツを着用していましたが、
- 3mmのセミドライのフルスーツではお昼前後の気温のピーク時間は暑かったため、ウェットスーツの上半身は脱いで下半身のみの着用
- 水に浸からなければ上下ラッシュガードのみでも平気で過ごせたが、足元などエントリーだけでも濡れてしまう部分はウェットスーツ着用なしだと肌寒かった
- 16時頃〜(17時迄)は風が冷たくなり体が冷えたので、ウェットスーツを上までしっかり着て、さらに薄手のウインドブレーカーを着用していました。
シュノーケリングなどもやりたいのであればフルスーツが必要です(逆にフルスーツを着ていれば寒さはほとんど感じず余裕で楽しめます)。
どっぷり海に入らないのであればセパレートスーツの下半分の着用だけでも良いかもしれません(エントリー時に濡れたところが冷えないようにするため)。
また、日差しがかなり強いので、サングラスはあった方が無難です。(海の中が良く見えるので偏光サングラスがオススメ)
沖縄・古宇利島にて個人でSUPをする際の注意事項
風の向きや強さに注意
釣り人に注意
島の外周は距離がある
結び
期待を裏切らないとても素敵なひとときを過ごせる場所です。
- 関連:
- 持ち込みSUPで毎回発生する「準備・後片付け」が快適にできるよう、準備・後片付けに必要なグッズや選び方、筆者のおすすめを記事にまとめました。こらもぜひ合わせてご参考にしてください。








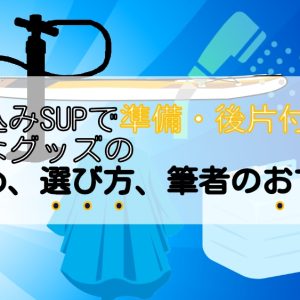



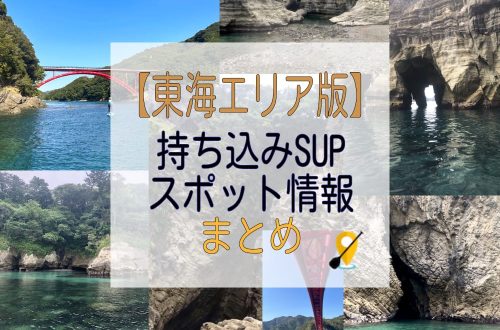

1件のコメント
ピンバック: